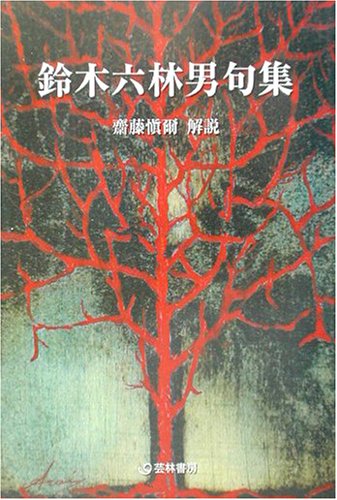平らかに心すべってゆくか。〈ひとところ黒く澄みたる柿の肉/岸本尚毅〉黒く、だけではなく澄んでいる。そこが甘いところでもある。〈はらわたの動くを感じ日向ぼこ/岸本尚毅〉不随意、つまり意識外の臓器が動く。体内で別の意志が働くのを恒星からの光で熱せられる地球で感じる。その別趣として〈椅子と人友の如くに日向ぼこ/岸本尚毅〉か。〈顔焦げしこの鯛焼に消費税/岸本尚毅〉この滑稽さは上手い。〈春塵やマクドナルドの黄なるM/岸本尚毅〉その真ん中のVはいつも埃をかぶっている。〈青き絵の中に白き日避暑の宿/岸本尚毅〉郷土画家の風景画が飾られた高原のロッヂだろう。のんびりと絵でも見て過ごす。〈ひつぱられ今川焼は湯気漏らす/岸本尚毅〉大判焼や御座候とも。この「漏らす」は中動態だ。〈くちばしの見えぬ向きなる寒鴉/岸本尚毅〉くちばしがないように見えてぎょっとしたのだろう。そういう寒さ。〈あたたかや石を境に違ふ苔/岸本尚毅〉多様なもののが境を決めることで共存する世界だ。〈始まりの終わりに似たる花を見る/岸本尚毅〉卒業と入学と。〈青き空甘茶に暗く映りけり/岸本尚毅〉青に何が加わって暗くなったのかと想像させる。〈明易やもの置けそうな凪の海/岸本尚毅〉きっと瀬戸内海や浜名湖などの内海だろう。
秋の雲子供の上を行く途中 岸本尚毅