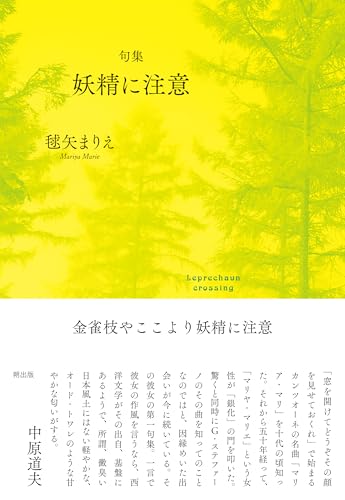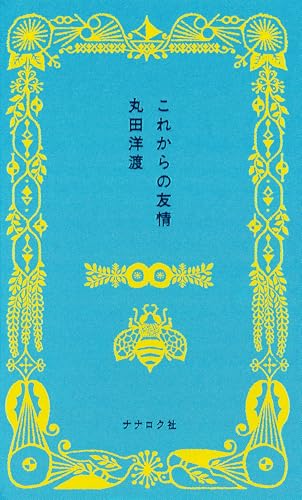-
フォン ノイマンは, 機械は自己再製が可能であることだけでなく, 機械がそれ自身よりも複雑な機械を作り出すことが可能なことも証明した.(ウィリアム・パウンドストーン著、有澤誠訳『ライフゲイムの宇宙』日本評論社)
- ウラム「再帰的に定義した幾何学模様」
-
コンウェイはフォン ノイマンの推論の方法を利用して, 自己再製可能な物体がライフゲイムで構成できることを証明した. (ウィリアム・パウンドストーン著、有澤誠訳『ライフゲイムの宇宙』日本評論社)
- 社會史盤 LITMASS
-
宇宙より大きくなりぬ竈猫/久保純夫(『識閾』小さ子社)
-
Kamâlist Türk islam üstünlükçü faşizme göre Türkleşmek ve Müslümanlaşmak medenileşmektir.(https://www.threads.com/@daranislxii/post/DUBSda5DEp_)
- 猥雑になるところかな蝶番/久保純夫(『識閾』小さ子社)
- 文化シミュレーター v1.4
- ゾンビ盤
-
刺青を移し終えたる螢草/久保純夫(『識閾』小さ子社)
-
なめくじら天皇制を統べており/久保純夫(『識閾』小さ子社)
-
木犀の戀が生まれる腋毛かな/久保純夫(『識閾』小さ子社)
- 旧字で新仮名という組み合わせの句集『識閾』
-
一回りして妻となる寒卵/久保純夫(『識閾』小さ子社)
-
白鳥の中でもあなた短気です/久保純夫(『識閾』小さ子社)
-
すなわち, 初期のCA理論は, 自らが活動しながら周囲と情報を交換し, そして, 自分と同じものを再生する過程を論理的に表現しようとしていた.(『セルオートマトン法』森北出版株式会社)
- 1970年代におけるライフゲームの爆発的なヒット→ハッカーの登場
- ノイマン近傍・ムーア近傍・マーゴラス近傍
- Alınteri、トルコ語の社会主義ブログ
-
Yaşıyorum. Taraflıyım. Bu yüzden iştirak etmeyenlerden nefret ediyorum. Bu yüzden kayıtsızlardan nefret ediyorum.(Gramsci: “Kayıtsızlardan nefret ediyorum”)
-
CA法は, 相分離, 蟻の歩く道, バクテリアのコロニー形成, 凝集, 溶岩の流れのシミュレーションなどに適用されている。(『セルオートマトン法』森北出版株式会社)
所以272
- Non transiri posse ab uno extremo ad alterum extremum sine medio.
- 2C PRINT MAKER版ズレやインク滲み、レトロな二色印刷風
-
イランのインターネット遮断(デジタルブラックアウト)は、スターリンクへのアクセスを遮断するため、軍事ジャマーを配備するに至った。(イラン、史上初の衛星インターネット遮断 スターリンクに「キルスイッチ」発動)
- 獅子鮟鱇詩詞
- 境界を超える仕事、ハンガン
- 死を殺す、死の回復
- 古井由吉の「のべつ束ね、のべつこぼれるもの」としてのことば
- Tokyo'nun Son Çocukları - Yoko Tawada 多和田葉子『献灯使』
- 多和田葉子の謄写版同人誌『神様の武装』300円・限定40部
-
反政府デモが続くイランで近距離無線を使った連絡アプリ「Bitchat(ビットチャット)」の利用が急増している。(イラン、ネット不要の連絡アプリ利用15倍に急増 デモを組織化)
- ZOO ZONE、をかべまさゆき
-
FIFAランキングとは別に、代表チームの強さを測る「World Football Elo Ratings」という指標がある。チェスのプレイヤーでもあった物理学者アルパド・エムリック・イロ氏が考案した計算式をフットボールに当てはめたもので、相対評価によって実力を表すために使用される。(FIFAランクより正確とも 「Eloレーティング」では日本は16位 モロッコ、イタリア、ベルギーよりも上)
- World Football Elo Ratings
-
フロレンスキイの考えにおいては、幾何学的一貫性に基づいた記述であるということが、記述された旅の現実性を保証しているということである。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- 非ユークリッド空間として一貫性をもつダンテ『神曲』
- 非ユークリッド空間と逆遠近法
- 演劇の舞台美術由来の遠近法
-
フロレンスキイの考えでは、ルネサンスに際立った発展を見せた遠近法は、ルネサンスの人間中心主義、人文主義という標語に反して、実際には人間の、世界からの自発的疎外である。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
-
フロレンスキイは言葉に身体性を認め、〈形〉として扱っている(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- フロレンスキイは、音素と形態素は言葉の身体、意味素は言葉の霊魂・エネルゲイア的要素だとする。
- 意味素はコードか?
-
フロレンスキイが線遠近法を批判するのは、記述方法である線遠近法が、ユークリッド幾何学的な記述方法である、つまり、均質で、等向的で、無限で、曲率が0である等の特徴を持つユークリッド空間を記述する方法であるにもかかわらず、その遠近法の対象となる生きた世界は、非ユークリッド的な空間であるという、記述と記述される対象との不一致にある。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
-
幾何学は力の場によって決定され、力の場は幾何学によって決定される。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
-
フロレンスキイの思想においた、もう一つの世界、天上的世界のは、地上から見れば逆向き、反転した世界なのであって、その世界への移行も反転によってなされる。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- フロレンスキイの天動説
- フォン・ノイマン近傍は4近傍、ムーア近傍は8近傍
-
そのような数学的世界観とは、具体的にどのようなものであるか。それは、不連続性が連続性に優越し、不連続性こそが世界の基礎であると見做す考えのことである。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- フロレンスキイの「数の同一」
-
フロレンスキイの考えでは、「死んでいる」事物を種・類の同一/区別のもとで捉えることはできても、「生きている」人格、リーチノスチに対してはただ数の同一/区別が適用できるのみである。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- 死を怖れるのは個を喪うからだろう。
-
フロレンスキイの見解では、人間と世界とは相互に反映し合い、相互に実体的な影響を与えうる関係にある。(細川瑠璃『フロレンスキイ論』水声社)
- 季語は逆遠近法かも。
所以271
- 謹賀新年、〈永遠のような一瞬姫始/以太〉
- 時局匡救事業と防遏
- 戦後政治史をとらえる上での亡霊としての内務省の重要性
-
内務省の裏庭で三日三晩にわたって公文書を燃やした「勤勉」な内務官吏(『内務省』講談社現代新書)
-
モッセはまず、府県から町村までの各レベルへ国の行政事務を分任し、これを住民代表が自らの問題として無給で引き受けることを「自治」と位置づけた。(『内務省』講談社現代新書)
-
大学で文学を専攻した人物を演劇検閲官として雇うようになっていく。(『内務省』講談社現代新書)
-
こうした議論の背後には、貧困に陥った本人が、働き、貯蓄をするという努力を怠っているからだという考え方があった。裏を返せば、勤勉に働き、貯蓄につとめていれば、かならず成功するはずだという考え方が、近代日本の形成期には広まっていたのである。(『内務省』講談社現代新書)
- 内務官僚・井上友一の救貧制度、「貧困を生まないような精神の土壌を作ること(「風化」)が最上位に置かれる。
- 風化>防貧>救貧が井上友一の救貧制度
- 大正デモクラシーとは、自明視された国家の至高性への問い直しと政府の統制外にある公共空間としての社会への関心
-
〈ヘッドフォン・ステレオを聴く この家にもうだれもいないことに気づいて/加藤治郎〉(「サニー・サイド・アップ」『加藤治郎アンソロジー1』書肆侃侃房)
- ↑逆に、の歌
- ベトナム古典詩協会/ベトナム唐律詩協会Hội Thơ Đường luật Việt Nam
- 新季語
- ミニ大区分ゲーム、郵便
- ポエム・イン静岡2026、1月25日、静岡県男女共同参画センターあざれあ502
- オープンミーティング「はなしてみる」、2月1日(日)14時〜、鴨江アートセンター301
- 個々の諸人格の方が絶対的根源性をもつか諸人格の一体性の方が原初的かで、ロシア哲学は人格主義と霊的共同体とに分かたれる。
- 全と個に関するフロレンスキイ思想の〈形〉
- 時間の石化、過去と未来の時間が共在する逆遠近法
- 逆遠近法はイコンであり日本画なのかも。
- 第二回くわだてとたくらみ賞
西生ゆかり『パブリック』左右社
〈等身大パネルのような新社員/西生ゆかり〉この明喩感覚には嫉妬。〈バナナの皮バナナの如く反りゐたる/西生ゆかり〉実を喪っても皮だけでそのものであろうとする。〈パイプ椅子引くや花茣蓙やや歪む/西生ゆかり〉俗により歪められる聖である。〈内側のやうな外側捕虫網/西生ゆかり〉アーモンドチョコレートじゃないけれど、でもどちらでも機能する。〈百円で買える光や夏祭/西生ゆかり〉こどもが好きなやつ。〈噴水が天使に戻りかけてゐる/西生ゆかり〉美しく広がるさまだ。〈蜻蛉飛ぶ蜻蛉の中が狭すぎて/西生ゆかり〉この発見、脳がうごく。〈鉄板に餃子の皮やクリスマス/西生ゆかり〉街っぽい。〈全員サングラス全員初対面/西生ゆかり〉奥ゆかしい。〈鍋焼やもうすぐ終はる資本主義/西生ゆかり〉具を持ってこない人も食べられる。〈白シャツや一人称の入れ替はる/西生ゆかり〉私→おいらだろう、たぶん。〈冷蔵庫と壁の間にずっと居る/西生ゆかり〉涼しいし落ち着く。〈避妊具は出来損なひの熱帯魚/西生ゆかり〉道理でときどき動き出すのか。〈どの塔も天に届かず糸蜻蛉/西生ゆかり〉未踏なりけり。〈水仙や無言電話に息少し/西生ゆかり〉ほのかに生を感じる初春である。〈夜出せば明日の手紙や柘榴の実/西生ゆかり〉いつの昔か速達か。〈両耳はとはに出会はず水の秋/西生ゆかり〉耳を澄まして水も澄んでゆく。〈音楽のはじめは無音冬の水/西生ゆかり〉音は水という感覚。〈髪洗ふ眼に海を育てつつ/西生ゆかり〉生きているから。
蘭鋳に生まれて意味が分かりません/西生ゆかり
所以270
-
生命とは死なしには存在しえないが/死後を知るものはいない(城戸朱理「海のメタファー」『海洋性』思潮社)
-
何事も指示しえない暗喩が/影ばかりを深くする(城戸朱理「人生の正午」『海洋性』思潮社)
- 城戸朱理の用語としての「人生の正午」
-
今、一羽の鳥が子午線を超えた(城戸朱理「真昼の覚醒」『海洋性』思潮社)
-
「あらゆるひとびとが、すべて詩人である時代がやつてきた」1953年8月。全日本損害保険労働組合情宣部が発行した「心に未来を 全損保詩集」は、こんなメッセージを掲げている。(詩をつくる労働者たち 時代に染み通った「機械のなかの青春」)
-
文化こそが、人が人の生存のためにつくり出した適応装置だという事実を確認する必要があるように思う。(北山忍『文化が違えば、心も違う?』岩波新書)
-
文化とは、慣習と常識の複合体で、この複合体はしばしば生態条件に裏打ちされている。(北山忍『文化が違えば、心も違う?』岩波新書)
- 遺伝子が文化によって淘汰されている。
-
文化は学習されるものである。たとえば、日本人として育つと、その文化にある慣習や常識を学習する。(北山忍『文化が違えば、心も違う?』岩波新書)
-
文化とは当該の生態環境に対応した「生き方」、つまり、慣習とそれに関わる常識の複合体のことである。(北山忍『文化が違えば、心も違う?』岩波新書)
- Orhan Veli、トルコの詩人
-
誤記からChatGPTが読み取った思想コア「文化は、誰かが無名のまま続けた行為の総体である」
- トルコ弓yay、Geleneksel Türk Yayı ・Osmanlı Yayı
- bakkal、トルコの地域密着型雑貨食料品店
- 牧民官としての内務官僚
-
洞木に言わせれば、明治開国以来、その存在を嘲笑してはならない集団は二つしかない。二・二六決起将校と、大東亜戦争中の一部の内務官僚だ。将校達はその純粋さ、官僚達は、戦争勃発当時からすでに敗戦後のシミュレーションをやっていたというその優秀さ、においてだ。(村上龍『愛と幻想のファシズム(下)』講談社文庫)
-
圧力はかけながらも、選挙管理事務は比較的誠実に実施されたことは特筆してよいだろう。(『内務省』講談社現代新書)
-
しかし狩猟社のフィールドには、社会的なものは、何一つとして存在しないのだ。(村上龍『愛と幻想のファシズム(下)』講談社文庫)
- ミクロなレベルでの「ファシズムの練習」としての地方文化行政とクリエイターの癒着
- komun、トルコ語
- 新潟の萬代橋の落書きの件についての吉樂蕗さんの意見を読めば読むほどアートと落書きの違いが描いた人ありきでしかない。
- dörtlük(トルコ語四行詩)、韻はuyakもしくはアラビア語由来のkafiye
- 平韻 (Düz Kafiye): aaaa または aaab
- 民謡韻(Mâni Tipi Kafiye)はaaba
- mâniはkoşaとも。
- 交差韻 (Çapraz Kafiye): abab
- 抱擁韻 (Sarma Kafiye): abba
- Yarım kafiye(半韻)母音1つだけ一致(例:a / e)
- Tam kafiye(完全韻)2音以上一致、savaşとyaş
- Zengin kafiye(豊韻)3音以上一致、yaprakとağlayarak
- Cinaslı kafiye(語呂韻)同音異義語を使う韻(民謡に多い)
- 視覚韻。日本語だと暮と魯、墓と基とかかな。
- 沖縄のさし草
所以269
-
アメリカの成長の奇跡の鍵は、たった一つの要因にあった。それは新しいアイデアを受け入れることであり、それが才能を獲得するグローバル競争における覇権を可能にしたのだ。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
-
経済的な観点からすれば、クリエイティビティは資本の一形態である。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
- クリエイティブ資本
-
私の理論において最も見過ごされがちでありながら、いちばん重要なポイントは、すべての人間はクリエイティブであるという点である。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
-
クリエイティブ・クラスの概念は、したがってエリート主義でも排他的でもない。事実、私は主に「知識労働者」「情報社会」「ハイテク経済」という概念に対する個人的な不満の結果として、これを創出したのである。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
-
クリエイティビティこそ、社会を平等にするツールである。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
-
社会は少数の才能に関心を示す一方で、より多くの人びとのクリエイティブな可能性については無視している。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
- なぜクリエイター界隈は文芸ジャンルをクリエイターから排除したがるのか?
-
人間のクリエイティビティの壮大な集合体は巨大な生態系であり、あるタイプの特性がほかを補完したり、ほかと共生したりすると考えられるからである。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
- ↑群衆によるネットワーク
-
基本的な考え方を三つにまとめよう。クリエイティビティは現代の最も重要な富の源泉であり、人間一人ひとりかわクリエイティブであり、あらゆる場所がクリエイティブな仕事に関わることに価値を置くものとする。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
-
全労働者の七割をも占める非クリエイティブ・クラスの労働者は、やりがいのあるクリエイティブな仕事をする機会を与えられたことがない。私たちは、結局のところ、巨大なクリエイティブ資本の蓄積機会を活用しないまま、封印しているのである。(リチャード・フロリダ、井口典夫訳『クリエイティブ・クラスの世紀』ダイヤモンド社)
- 多文化共生社会の方針に反する浜松クリエイター・ファシズムというありかた
-
二十世紀的な隠喩は崩壊する/危機的な状況においては/合理主義の亀裂から/民族的な習俗がよみがえったりもする(城戸朱理「国境」『火山系』思潮社)
-
墜落が主題であるかのように/海岸に猛禽類が堕ちてくる(城戸朱理「遊星のように」『火山系』思潮社)
-
自律神経がざわつくと/地上は死んだ比喩に覆われて見えなくなる/言葉には余計なものが積み重なっていくので/ときどきは、詩で洗わなければならない(城戸朱理「死んだ比喩」『火山系』思潮社)
- Pekmez、グレープモラセス・ぶどう糖蜜
- たとえば文芸の全体性への畏怖?
-
マッコウクジラは一生のうち/三十分しか眠らない(城戸朱理「海の色になって」『海洋性』思潮社)
- マッコウクジラ、一日九十分くらい眠るらしい、半球睡眠。でも一生三十分は詩的
-
千人の失踪者の捜索願いが出され/千人の失踪者はより確かに失踪した(城戸朱理「手紙が届かない、夏」『海洋性』思潮社)
-
袋井市役所2階・市民ギャラリー令和8年1月11日(日)~20日(火)のぶすま書院一周年展(俳句、短歌、川柳および絶句)(広報ふくろい 令和7年12月号)
- 祝福に飽きてニヒリストになった人がプロパガンダ的宣伝を扱える。
- 攻撃しつづける狩猟社宣伝局
所以268
-
自治体文化財団とは、自治体が出捐した文化芸術を専門に扱う団体である。文化振興財団とも呼ばれる。(松本茂章編『はじまりのアートマネジメント』水曜社)
- 官僚制の逆機能
-
しかしながら、全体としては「地域活性化」に流れやすい重力が、スポンサーが公的機関であることと、官僚的な文章術によって、生じてしまう。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- アートプロジェクトを主催する3パターン↓
- A.行政主導のアートプロジェクト、B.地域住民や関係者が企画するボトムアップ型のプロジェクト、C.アーティスト自身が新しい表現を目指し、既存の施設を飛び出して行うアートプロジェクト
- 静岡県浜松市の詩丼はどちらかというとCかな。ボトムだけどアップしていない、ボトムのまま
-
1つは消費者のニーズは、製品という物体そのものではなく、その製品を消費したときに得られる便益で満たされるからである。(松本茂章編『はじまりのアートマネジメント』水曜社)
- アートマネジメントと社会教育士
-
アートマネジメント人材は「アートの人」である必要はない。文化施設や文化芸術団体を経営するとともに、行政とタフな交渉を重ね、市民らと連携し、企業などの民間から寄附を集める。こうした総合的な能力が問われる。(松本茂章編『はじまりのアートマネジメント』水曜社)
-
「地域アート」とは、ある地域名を冠した美術のイベントと、ここで新しく定義します。/「地域アート」は、「現代アート」から派生して生まれた、新しい芸術のジャンルです。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- 地域アート Community-Engaged Art Project
-
物質としての作品よりも、そのような「関係性」それ自体の快楽が「美」として認識されているかのようである。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
彼らは、とても素直なのである。だからこそ、本格的に「美」について構造が変動しているのではないかと考えざるを得なかった。/後述するように、これらの元になっている考え方が、カウンターとして打ち出された時には斬新なものであったと推定される。だが、それらの批評性が正しく認識されないまま、のっぺりと広がっていくような現状に、危惧を覚える。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
アートは、このように、コミュニケーションの生成に関わるものへと変化しようとしている。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
ビショップの批判を大胆に要約するとこうなる。関係性の美学はマイクロ・ユートピアの傾向、すなわち、内輪で盛り上がっているだけで排除的な傾向がある。美術の制度などにある程度適応している人間などの「関係」でしかなく、スラムやゲットーに住んでいる人との「関係」は排除されているのではないか、と(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- ↑クリエーター・ファシズムとマイクロ・ユートピア、浜松市のクリエイターから排除された文芸人・文化人やオタク的な人々
-
この会話で腑に落ちたのは、関係性の美学が、マイクロ・ユートピアすなわち「安定した調和的な共同体のモデル」を志向しているという点である。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
真に問題なのは、歴史の中で発展してきたこのような芸術の伝統や理論を、相も変わらぬ日本の地方都市的なものが簒奪し、かなり自分の都合の良い場所だけ恣意的に抜き出し、自己肯定的に使い始めていることなのだ。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
このようなアートプロジェクトが、批評など他者からの言葉を排除しがちである傾向があることもまた指摘されている。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
しかし、現在の地域アートはそうではなかった。そこは「批評」が勝利し、「王」になれる世界ではない、むしろここでの「王」は「当事者」と「地域」である。あるいは「王」が廃絶された、民衆たちの民主主義がユートピア的に実現している(という錯覚がある)のかもしれない。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
ひとまずまとめると、関係性の時代の芸術において「大きい関係性」を扱う傾向を持っているのが「地域アート」であり、「小さな関係性」を扱うのが「友達アート」であるとここで仮に定義することにしよう。(美術手帖「友達アートの射程 じゃぽにか論①」)
-
ここで奥村の想定する「友達」が、日常言語における「友達」と異なっているのは、(その告知をあらかじめ知っていた者に限定されるとはいえ)、それがほぼオープンな状態であるという点である。知らない人でも「友達だと思う人」は参加できるということは、勝手に友達だと思い込んで参加する人間の出現可能性を排除していない。これは明らかに、通常の「友達」とは異なる。むしろ、奥村はここでこれまでのよくある「友達アート」における「友達」概念を改変することをこそ行おうとしているようだ。(美術手帖「友達アートの射程 じゃぽにか論①」)
- ↑友達の再定義、オープンな友達かクローズドな友達か
-
それと似たような意味で地域の滅亡の際の鎮痛剤として芸術が機能すればそれでよいという覚悟の上で、芸術を再定義しているのだとすると、北川フラム個人の芸術観を単純に否定はできない。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- 鎮痛剤としてのアート、しかし鎮痛剤以上のものをアートに期待するならば叛逆の政治思想と芸術と社会とを連関させなければならない。かつて全共闘以後の日本ができなかったことを。
-
新しい世界の可能性を開示することで、根本的に別種の政治の可能性を提示することが、芸術にしかできないことではないか。政治思想や社会の動向に随伴し、既存の権威を用いて自己正当化することは、美術固有の存在価値を毀損しているのではないか。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- 世界を全的に変えてしまうアートの鮮烈な力を活かす。
-
藤田 地域主義はグローバリゼーションの付随現象として誕生しなおしている。一般的に、全世界的にグローバリゼーションが遍在し、その反動として民族主義とナショナリズムが昂揚しています。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
星野 たとえば、毎日厳しい労働を強いられている人間がふとある詩を読み、そこから自分も新たに何かを創造するということがありえる。ここには、制作者と鑑賞者の直接的なコミュニケーションが存在するわけではないですね。むしろこうした出来事が起こりうるのは、「作品」を媒介として三者のあいだに「距離」が存在しているからです。こうした既存の社会関係を宙吊りにする力を、ランシエールは芸術作品の本当の潜勢力だとみなしています。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- ↑星野太
-
星野 ある種の巨大な流れが情念的に形成されていくときに、水を差していったり、違う見方があると指摘するような、批評の営みには、ファシズム的な空気に抵抗する部分もあります。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
つまり、アートプロジェクトは、二〇〇〇年代を通して、その社会性が可視化されると同時に、その批評性の弱さによって特徴づけられるようになったと言えるだろう。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
田中 僕は、正直なところ、日本のなかでは「美術」という制度自体がなくなってしまってもいいんじゃないんだろうかと、どこかで思っています。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- ↑田中功起
-
田中 「アート」には興味がない、でも「アーティスト」になりたいという人はいて、そういう人がいなくなって、むしろ本当に作りたい人たちが表面化していくわけだから、いいことだと思う。やっとそういう人たちが見えてくる状況になる。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
-
藤井 ゼロ年代に入ると、地域アートを推進する人たちが創造都市論を引き合いに出してきたじゃないですか。地域再生の鍵は工場の誘致ではなく、創造的な社会集団を地域にどう誘引するかといった議論です。(藤田直哉編著『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版)
- ↑藤井光
- 創造から生成へ
-
都市において、比較的低所得者層の居住地域が再開発や文化的活動などによって活性化し、結果、地価が高騰すること。(ジェントリフィケーション)
- Gentrification
-
アーティスト達がいい感じに文化度を上げた結果オシャレなカフェやギャラリー、ブランドが集中するようになり地価が高騰し、アーティスト達は近隣地域に移っていくという流れが発生し、その後もその流れは続いてベルリンが飽和すると近隣の地方に第二第三のベルリンと呼ばれる場所が生まれています。(https://www.threads.com/@sankakudo1026/post/DSPv2hFEgFP)
-
経済的に苦しくなったアーティストやアーティスト志望の人が物理的な移動ではなくデザインなどより経済にコミットしやすい方向に移行していっている傾向があるように思えます。(https://www.threads.com/@sankakudo1026/post/DSPv2hFEgFP)
-
アーティストやクリエイター、近隣地方の行政はそうした流れを見てきているので、アーティスト・クリエイター側は自分達で自分達の首を絞めないように色々試みたり、行政側はジェントリフィケーションを上手く起こそうとしつつアーティストやクリエイターがジェントリフィケーションによって排除されないセーフティも作ったりなど色々工夫をしているようでした。(https://www.threads.com/@sankakudo1026/post/DSPw10mkolc)
- Sait Çetinoğlu、トルコ語、トルコの独立研究者
所以267
- ジェイソン・アンダーソン
- Yeni Komünizm 新しい共産主義(トルコ語)
-
損害賠償制度に関する変更/書留郵便物、普通小包、保険付郵便物又は国際スピード郵便物に亡失、損傷等が発生した場合は、差出人さまが、自己の権利を受取人さまのために書面により放棄した場合に限り、受取人さまが賠償金を請求する権利を有することと変更されます。(新万国郵便条約の施行に伴う国際郵便サービスの一部変更について)
-
かく孤独を自分一人の問題とせず、人間すべての問題とし、更に生物すべての問題として感得しておるところに杜甫の特色があるといえよう。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
- 轉蓬=回転草 tumbleweed
- 李白の不遇
-
不遇とは、才能に相当する地位が与えられないことである。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
- 太乙膏はカレーのにおい
-
すなわち中立性とは、デリケートな問題について沈黙を通すことを意味するのではない。諸民族間の融和に役立つすべての事柄について、大会の場で怖めず臆せず議論することを意味するのである。(ウルリッヒ・リンス『危険な言語』国書刊行会)
- ただの道具である言語に、中立も危険もないのだけれど、危険を見出そうとする人もいる。
- korespiond-i 文通する。korespondo 文通
-
度を越したスターリン主義について、外国人文通相手に包み隠さず書く勇気の持ち主は、どうやら少なくなかったようだ。(ウルリッヒ・リンス『危険な言語』国書刊行会)
-
ムッソリーニ治下のイタリアは長らく、中立主義運動の主張を支える根拠でありつづけた。極端なナショナリズム政権下でもエスペラントが存続できる、という主張である。(ウルリッヒ・リンス『危険な言語』国書刊行会)
-
エスペランティストに対する迫害は、知る人ぞ知る宝の山、すなわちエスペラントについて教えてくれる。エスペラントが誕生の瞬間から、近代コスモポリタン主義の表現手段として、政治家が賛同したがらない種類の欲求を代弁してきたことを。(ウルリッヒ・リンス『危険な言語』国書刊行会)
-
けれどもエスペラントは、ほとんど生まれた直後から敵意に直面しなければならなかった。(ウルリッヒ・リンス『危険な言語』国書刊行会)
- agos、トルコ語
- 朴玟奎 박민규
- 失郷民 실향민 、韓国語という日本語とは違う漢字体系の国で
- 文以載道、朝鮮儒教における文のありかたとしての啓蒙
- 日刊ベストストア(イルベ 일베)
- 啓蒙から疎通へ
- 疎通の困難さと脱構築と
所以266
- Evrensel、トルコ語
-
コール天は、織布、緯パイル糸を切るカッチング、染め、仕上げなど細かな分業により生産される。天龍社産地(静岡県磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市)が日本の主力産地(日本唯一のコール天産地、存続が切実な課題 海外製にはない柔らかさをアピール)
-
明明上天/照四海兮/知我好道/公來下兮/公將與余/生羽毛兮/升騰青雲/蹈梁甫兮/觀見三光/遇北斗兮/驅乘風雲/使玉女兮(淮南操)
- 見乞兒與美酒/以免破屋之咎
- 令和人文主義は人文知や教養を商品として上から下へ販売し、擬似知識人の量産による階層化をもたらす。
- 群衆たる一般市民が代議士やクリエイターへ政治や芸術を代行させることなく社会に自ら参画するための知識を配布する、有機的知識人による令和グラムシ主義へ。
-
Un’approfondita ricerca genealogica mostra che la nonna materna di Antonio Gramsci ha sposato il fratello di una bisarcavola, ossia una nonna di una bisnonna, di Giorgia Meloni. Ma procediamo con ordine.(L’inaspettato legame familiare tra Meloni, Letta e Gramsci)
- アントニオ・グラムシの母方の祖母は、ジョルジャ・メローニの曽祖母の兄弟、つまり曽祖母の祖母と結婚していた?
-
グリズリーは代謝作用で発情する。俺達は大脳で発情する。(村上龍『愛と幻想のファシズム(上)』講談社文庫)
-
吾所以有大患者、爲吾有身。及吾無身、吾有何患。(老子)
- 吉田一穂の史前領土
- 琵琶湖畔長浜のラリルレロ書店の詩人、武田豊
-
③令和人文主義「(こいつら、めんどくせー)わーい、“知”って楽しいー⇒(若手)20代以上のクリエイターや在野研究者やビジネスマンなど(世界一わかりやすい「令和人文主義」入門)
- ニクトグラフ nyctograph
- Introducing the Hipster PDA、Parietal Disgorgement Aid、頭頂部嘔吐補助器としての情報カード
- 短歌時評「短歌の主体」、作中主体からあいだの主体へ
-
固時俗之工巧兮(離騒)
- 饒舌rapping:暗語・俗語・俚語、詞(content)・腔(flow)・吐(delivery)
-
静岡サイファー 自閉症と共に生きるラッパーとして注目され、Youtubeにアップされた楽曲「人間失格」で脚光を浴びたGOMESSが立ち上げた静岡サイファー。(日本中で勃発!最近話題のフリースタイルラップ「サイファー」とは!?)
-
秦末漢初になると、「時」とか「天」とかの責任であることを自分に言い聞かせて、それを歎くよりも、むしろそれによってあきらめるという気持があらわになった。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
- 項羽の「時不利」「天之亡我」、理法的な「時」「天」
-
上品無寒門/下品無勢族(晋書)
- 下品は仏教以前からある身分制の用語だよ。
- 塊(つくねん)
-
要するに左思の孤独感は、「地勢」の不利を意識せるところから来たものであった。この「地勢」の不利の意識は、すなわち当時の社会の階級差に対する反抗意識であるといい得よう。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
-
鮑照において、左思と同じく、家柄の卑賤を思い起こすことによってやるせない孤独の情を慰めようとしていたことを見るとともに、左思にはなかった、自己の性格を思い起こすことによって孤独を慰めようとしていたことが見られるからである。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
-
我既不狂、難以獨立,比亦欲試飲此水(袁粲「妙徳先生伝」)
-
ところが、一度自覚したが最後、生きておる限り、どうにも免れようのない孤独感が二つある。その一つは生命のはかなさの歎きから来るものであり、もう一つは、人間は所詮一人一人のものだと意識するところから来るものである。(斯波六郎『中国文学における孤独感』岩波文庫)
- フィリバスター filibuster だけどニカラグア大統領ウィリアム・ウォーカーとかめちゃくちゃ
- ユナイテッド・フルーツ社→チキータ・ブランド
- 詩的真実と視点操作
- McOndo マッコンドとマコンド
- 漏刻博士・宮道弥益
- 出版業界は衰え、出版文化は栄える。
-
盆踊りは、大多数の人たちで時空を動かす、幾何学模様のようだ。多大な影響を与えるかもしれない盆踊りの可能性と熱の伝導率の高さに、時にくらくらする。(イマジン盆踊り部 大嶋櫻子「BonZine」Summit2025Yokohama)
毬矢まりえ『妖精に注意』朔出版
〈花冷の昼映画館みなひとり/毬矢まりえ〉「みなひとり」の社会観がいい。〈小春日や臓器を持たぬぬひぐるみ/毬矢まりえ〉「小春日」が小気味良い。〈花ミモザ涙は数へらるる名詞/毬矢まりえ〉涙は数えられるという驚きがある。〈黄水仙ドールハウスのドール留守/毬矢まりえ〉-ha-u-suと-ru-suの押韻が心地よい。〈輝けるクリスマスツリー根を持たず/毬矢まりえ〉輝いているものが必ず地に足ついているとは限らない。〈巨大ビル建ち上がるまでたんぽぽ黄/毬矢まりえ〉壮大な建築現場とちっぽけな野の対比。〈玉子パック秋陽を十に小分けして/毬矢まりえ〉卵のないパックがなぜか転がっている景としておもしろい。〈夜長の椅子に恐竜柄エプロン/毬矢まりえ〉平和の家庭そのものといった感じ。
春土掘るいつか眠る日のために/毬矢まりえ
西村和子『素秋』朔出版
〈花篝祇園の空の暮れきらず/西村和子〉木の花と人の花と。〈駅員の申し送りに燕の巣/西村和子〉のどかな田舎の、きっと単線の駅の景だろう。〈遮断機のぎくしやく上がり梅雨晴間/西村和子〉通れる道の開けたさまと、梅雨の雲の晴れ間と。〈隠れ棲む文士と女優木槿垣/西村和子〉宮城まり子と吉行淳之介を想像した。木槿の鮮やかさとまばらさがいい。〈検疫を待つ船あまた春寒し/西村和子〉コロナ禍を思い出した。〈マフラーや口ごもるとき句が生まれ/西村和子〉音にならない音からことばができてゆく、マフラーの色を媒介に。〈向日葵の待ち伏せに会ふ夜道かな/西村和子〉向日葵のヒトガタ感をよく表現している。〈歩み寄るほど噴水の音粗雑/西村和子〉発見の句だ。〈蛇衣を脱ぎ少年の声太る/西村和子〉ふしぎな相関関係。〈かき氷一人一卓占領し/西村和子〉夏の小屋だろう。それぞれ他人同士でかき氷を食べる。〈冴返る我が身にいくつ蝶番/西村和子〉ガチガチ音をたてる。
愚かなる人類に年改まる 西村和子
所以265
-
『パターソン』の大きな魅力は詩。つつましい日常の中で、時にそこから少し離れて詩が生まれる瞬間に静かなダイナミクスがある。劇中詩の多くを提供しているのが、NY派詩人のロン・パジェットです。(現代の詩人が惹かれ読み漁る、20世紀の素敵な詩人たち)
-
偽の問題には答えがない。したがって、人々はその周囲をただ堂々巡りする。そうして、結局は力関係によってすべてが決定されていく。偽の問題によって得するのは誰か? それは、既に権力を手にしている者、既に決定権をもつ者である。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
-
彼らは偽の問題を流布し、人々から思考の自由を奪う。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
- 友人や知人との結束が悪いのではなく、友人や知人との結束以外に原理を持たないことが悪い。方針を持てばその方針に賛同する人が加われる。
- 可能的なものと必然的なものの同一性を見るとき、意志は偽の問題だ。
- 謝金
- Pontos Gerceği、トルコ語
-
構造は還元された一般性を扱い、機械は反復される特異性を扱う。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
- フェミニズムは父を殺したい(憎悪)と同時に父に取って代わろう(愛)とする。
- 普通精神病 psychose ordinaire
-
権力は、高い所だろうと低い所だろうと、とにかくどこかから来て、主体に働きかけ、その主体が「本当はやりたいこと」を抑制して、何かを行為させる。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
-
人々は自ら進んで搾取や侮辱や奴隷状態に耐え、単に他人のためのみならず、自分たち自身のためにも、これらのものを欲する。政治哲学は、それを問わねばならない。この地点に到達しない限り、政治哲学は、抑圧するものと抑圧されるもの、支配されるものと支配されるものという図式を決して抜け出すことができないだろう。したがって、下から、「低い所」から来る実におぞましい権力なるものをつかむこともできないだろう。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
- 著作権があるから創作する人がいるのではなく、創作する人がいるから著作権がある。
- みんなで創造することやみんなで連句を巻くことと曖昧な著作権
- 著作権の曖昧な方が多く人の心をとらえる。
- Politika、トルコ語
-
結局のところ私の認識としては、文フリは既存の出版流通網と同様、書籍なるものをめぐる「なぜか現状使えてしまえている(ただいつまで続くかはわからない)優れたインフラ」として、地方開催のものも含めて可能な限り使っていくべきであると思っている。また一方で、文フリ以外の少し小さめなイベントやフェスのようなものをどんどん勝手に並行してやるべきだとも思っている。(【全編公開】「文学フリマは何を代表し、いかなる場となったか――あるいは小説・詩歌の実作者である私らはなぜ「評論」カテゴリを選んだか」(山本浩貴))
- 文学系中小イベントを主催しようよ
-
私らは多少ダサくてもぐずぐずでも紋切り型でもいいから何かしらのキュレーションをもっとはっきりと体現すべきであり、こういうメンツがいて、こういう界隈があって、といった雑な見通しをどこかで聞きかじった人らや新たに生まれた若者がだべれるような状況くらいは作れるようにならないと未来はない、しかもそれは何度も何度も数年ごとにあちこちで行なわれるべきだ、なぜなら私らは老いるし忘れるし世界は変わるしみんな死ぬから、と私は思う。(【全編公開】「文学フリマは何を代表し、いかなる場となったか――あるいは小説・詩歌の実作者である私らはなぜ「評論」カテゴリを選んだか」(山本浩貴))
-
「日本の歴史の新しい時代を提案します。1465年から1551年までの期間を『山口時代』と呼ぶべきだと考えます」(日本史に「山口時代」を設けよう 大内氏を研究する米大教授が提唱)
- 大内政弘・義興・義隆
-
僕達の紙飛行機はいつまでもただよいながら流れていった/早坂類(『写真歌集 ヘヴンリー・ブルー』RANGAI文庫)
-
頭蓋骨ひとつたずさえ旅をするいのちがひとつみどりの丘を/早坂類(『写真歌集 ヘヴンリー・ブルー』RANGAI文庫)
-
一九六五年、汚物運びの男の肩にかつがれていたあの豊穣あのおおぞら/早坂類(『写真歌集 ヘヴンリー・ブルー』RANGAI文庫)
-
あした来るひとりの遅刻者のためさいごの果実は穫らないでおく/早坂類(『写真歌集 ヘヴンリー・ブルー』RANGAI文庫)
-
ドアノブを探すことだ 夢の先の そしてそこから逃げてしまえ/早坂類(『写真歌集 ヘヴンリー・ブルー』RANGAI文庫)
所以264
- 撲飛
-
一部の批評家からは「偶然の拭き跡も作品の一部として残すべきだ」との声も上がっています。(美術館のボランティアスタッフが現代アートを“汚れ”と勘違いし、トイレットペーパーで拭き取る(台湾))
-
「制作」あるいは「詩 (作) 」の意のギリシア語。 poiēsisの形容詞形 poiētikēに由来する poeticsは普通「詩学」と訳されるが,poiētikē technēないし poiētikē epistēmēは字義的には「制作的知識」ないし「制作論」の意であり,詩学よりは広義である。(ポイエシスpoiēsisブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
-
その人の業績に注目し、客観的に伝える場面では、存命中の人でも、あえて「さん」を付けない場合もあります。(「さん」の付け方)
- снохачество
-
聯詩は十二音句の四行構成ですから、これは四行詩とも言われましょう。(一戸玲太郎「聯詩作法その三」『甲田の裾』第廿五巻第二号)
- 聯詩は五七・七五だけでなく六六、四四四など。脚韻より頭韻を尊ぶ。とはいえさまざまな頭韻パターンと脚韻パターンがある。
- 新定型詩誌『聯』 1938-1942 聯詩運動の拠点
-
風まよふ憤怒(いかり)の岩間/顔血ぬり花は青ざむ/聞えをり幼な子の息/かがやける海展(ひら)け行く(佐藤一英「よみがへり」)
- ↑頭韻はaaaa、脚韻はなし。
-
透らざるつめたきおもて/閉ざせるは燃ゆる母の手/霧消せよ細きゆびもて/戸の外につらぬ餓あり(佐藤一英「内外」)
- ↑頭韻はaaba、脚韻はaaab
-
淀みある聲は碧かり/宵に見し鳥は白かり/夢消ゆる星あるあたり/よろづよに映ゆる雲あり(佐藤一英「千代田の堀に立ちて」)
- ↑頭韻はaaaa、脚韻もaaaaだけどすこし硬いかな、文語だから? 文法韻だから?
-
雲裂け散り 年めぐれり/狂ひし空 極まる道/暮れゆく老 今こそ知れ/薫ずる花 身を染めたり(一戸玲太郎「うつし身」)
- ↑頭韻はaaaa、脚韻はなし。
- 一戸玲太郎『連詩集 椿の宮』PDF
-
武蔵野に春はまた來ぬ/麥笛に興ぜしむかし/とほきゆめ黑穂を摘めど/友どちに語る術なし(深谷なみき「麥野」)
- ↑頭韻はaabb、脚韻はabcb
- 一戸玲太郎は一戸謙三とも
-
【定形詩試作―日本詩韻律の解明】方言詩運動を展開した謙三は、やがて定型詩の創作に舵を切っていきます。「日本詩の伝統を西洋詩の理論から検討し、やがて西洋詩には全くない超個人主義精神を日本詩の過去に発見し、それを基礎として日本詩を世界詩歌として樹立しよう」(「津軽方言詩の事」)と謙三は考えていました。昭和13年、佐藤一英が主宰する四行定型詩「聯」の同人となり、多くの聯詩、論稿を発表します。(『青森県近代文学館報』)
- 遠州聯詩
- しずおか連詩と遠州聯詩
-
ドゥルーズは「変わる」(=生成変化)ということについて徹底的に考えたが、「変える」(=変革)ということは考えていない。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
- 諸概念の列島、諸概念の群島
- 新しい郵便用語集
-
無人島の無人状態は、単にその島に人がいるだけでは消え去らない。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
-
無人島の無人状態が崩壊するためには、人が住まうだけでなく、他者による知覚領域の構造が起きなければならないからである。(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』講談社学術文庫)
- AZRhymes、韻辞典
-
インド大臣とインド総督の関係はインド大臣がロンドンから命令を発し、現地に派遣されるインド総督がその命令を実行することが建前だったが、インド総督はあくまでインド皇帝(イギリス国王)の名代(Viceroy)であってインド大臣の代理(Agent)ではないとも定められていた(インド大臣)
-
インド大臣はインド総督府の駐英大使に過ぎない
- YOSHINORI NIWA
所以263
- 詩丼改2026年9月27日@浜松市
-
もはやスタッフと利用者の垣根もない。(『ただ、そこにいる人たち――小松理虔さん表現未満、の旅』認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
-
表現未満とは、誰もが持っている自分を表す方法や本人が大切にしていることを、取るに足らないことと一方的に判断しないで、この行為こそが文化創造の軸であるという考え方です。(『ただ、そこにいる人たち――小松理虔さん表現未満、の旅』認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
- 表現未満、プロジェクト
- ↑レッツはちゃんと文化を定義している
- でもレッツは扱いとしては垣根を設けないけれど、人の分断を前提としている。だからこそレッツが成り立つ。それに対抗するために人とクリエイターを分断していたら対抗できないどころか同化してしまう。
- 「表現未満、」という言葉そのものは表現と表現ではないものの分断を前提とする。しかし人間には自由意志などほぼないのだから表現か否かを分けられないはずだ
-
新しい関係を開く。そこから始まる。出会い直す。/ぼくにとって「表現未満、」は、いま、そんな言葉になりつつある。(『ただ、そこにいる人たち――小松理虔さん表現未満、の旅』認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
-
しかし、「表現未満、」は何かを明確に指し示したりはしていない。なんとなく、ふわっとしている。しかし実は「表現」に対してのアンチテーゼでもあり批評でもある。いわゆる巷で言われている表現とは一線を画して、新しい文化を切り開けるかも!といった挑戦である。(久保田翠「今年、小松理虔さんと旅をしました」『ただ、そこにいる人たち――小松理虔さん表現未満、の旅』認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
- 私は表現に「未満、」は設けない。一線も隠さない。うめきもいびきもまた詩だ。おもしろいと思うかは別だけれど。
- 障害者の特異性もクリエイターの特異性も認めない、特異な人とそうではない人を区別しない。宣伝文句に「特異」を使わない。
- 南アルプス地域個体群のツキノワグマ
- 超小型カメラPIXICAM(株式会社ハック)のTIME.TXTに書く日時設定方法は取扱説明書のとおりだとうまくいかない。「2025.11.11 14:05:00 Y」の形式が正解。
- クリエイターによる非クリエイター軽視は急にはじまったわけではない。その端緒は商業による非商業軽視にある。資本主義だ。
- 「誰かが傷つくから」「ヘイトスピーチだから」という理由で議論を避けていくと、まずは選挙結果で議論を避けられた側が勝つだろう。それで勝たなくても紛争になる。
- serbestiyet
-
リーダーシップにおいては、人文学の確かな基礎があれば、より適切な意思決定が可能になる。難しい問いを立てる場面では、人文学の素養が倫理的課題を解決するための助けとなる。そして、私たちは常にそうした課題に直面している。(シスコの幹部が今後「人文学的素養」が不可欠になると考える理由とは)
所以262
- 〈太陽錠剤 ふしぎと青い地下室に閉じ込められていた頃のこと/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)夜の隠喩として。
- 〈水になったピアノを弾いて少しずつ元のピアノに戻してあげる/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)逆塚本邦雄
- 〈ハンカチの鳥の刺繍を避けながら白い布地で涙を拭いた/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)痛いからね
- 〈成長が老いに転じていくところ 蜜柑畑の素敵な勾配/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)息切れしながら
- 〈花びらが教室内に入ったら掃かれて終わるから閉めた窓/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)扱い方が悲しくて
- 〈ふと 自分の気配がして振り返る 玄関が岬になっている/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)すぐそこに境界がある
- 〈降ろしたあとやっぱり降ろすんじゃなかったってバスにさえ思っていて欲しい。/丸田洋渡〉(『これからの友情』ナナロク社)句点がある。生きている価値を、重みを感じたいから。
- 枝状分岐宇端末点
- sendika.org、労働者のためのウェブサイト(トルコ語)
-
制度化された差別ではなく、人類が生きのびる上で必要な本質的な「差別」、人類を動物に含むという前提での「差別」を擁立しなければならない、というのが二人のとりあえずの結論だった。(村上龍『愛と幻想のファシズム(上)』講談社文庫)
- Zohran Kwame Mamdaniزهران ممداني
-
Bilim insanları, Tyrannosaurus rex’in bilinen en yakın atasını buldu. Yeni tür Khankhuuluu, dinozorların evriminde eksik halkayı tamamlıyor.(Tyrannosaurus’un Atası Keşfedildi: Khankhuuluu)
- 「影響力のある人」が存在するためには無思考でロボットのような影響をそのまま受ける人が必要だ。
- 能動意志の無限後退
-
京都から西には徳川の譜代大名を置かないのが関ヶ原合戦後からの一貫した領地配置の原則であったが、(家康はなぜ「豊臣との共存」から「大坂の陣」へと方針を急転換したのか?――近世史の第一人者が注目する「駿府城火災事件」)
- 名誉毀損罪と侮辱罪を併せて言論罪と呼ぶ。
- 「人が死んでいるんだよ」は便利な言葉、言論と死に因果関係があったかのように演出できる。
- 言論罪や性犯罪は広義の政治犯を出しやすい。
-
我々は意志の力では生きていない。脳と環境の相互作用によって、自動的に体を動かされ、全て事前に決まっているプログラム通りに反射を繰り返しているだけだ。意志で作っているように見えても、全ての行動は環境からの刺激に対する、反射なのである。(妹尾武治『未来は、決まっており、自分の意志など存在しない。』光文社新書)
- 心理学的決定論
-
小児性愛は、脳の個性であり、同性愛、異性愛と同列に語ることができる可能性がある。(妹尾武治『未来は、決まっており、自分の意志など存在しない。』光文社新書)
- つまり小児性愛とは外側前頭前皮質と海馬の活動レベルの有意の低さ
-
人民日報は6日の論評で、人民という言葉は「公的性格と深い政治的含意を持つ。特定の社会的情緒と公共の利益を体現するものだ」と指摘。この言葉を「冒涜(ぼうとく)してはならず、誤用も許されない」と付け加えた。(中国の「人民珈琲館」、人民日報に批判され謝罪 名称変更を発表)
-
意識とは情報であり、生命とはその情報を増やすために配置された「なにがしか」(存在)である。(妹尾武治『未来は、決まっており、自分の意志など存在しない。』光文社新書)
- 世界の本質は情報説