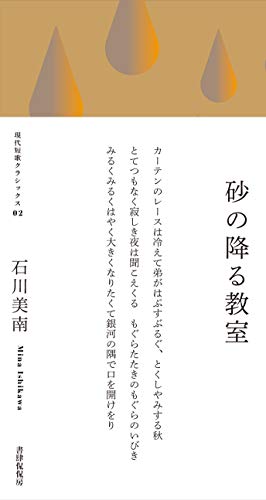〈白雲がとてもまぶしい春の日にあなたと椅子を組み立ててゆく/江戸雪〉組み立てるのはなんでもいいけれど、椅子なのがいい。居場所ができるから。〈ストライプの日傘をさして川へゆくときどき風が胸をぬけつつ/江戸雪〉大阪の運河と少し日の強すぎる町並みを思う、工業団地とか。〈降る雪にあしたの傘をかたむけて境界線のような道ゆく/江戸雪〉道は、人と人とをつなぐように見えて、実は人と人とを隔てる境界線なのかもしれない。〈電話してほしいとメイルにかいたあと瓶にのこったアーモンド食む/江戸雪〉青酸カリはアーモンドのにおいという。〈3ミリのボルトは箱にしゃらしゃらと風呼ぶように擦れあっている/江戸雪〉大阪の鉄工場の景だろう。運河の水音も聴こえそう。〈水無月は青い時間といつからかおもいておりぬ麻かばん抱く/江戸雪〉六月ならばその青の感覚はある、麻かばんの手触りにもそれはある。〈誤解されだめになりたる関係を舟のようにもおもう窓辺に/江戸雪〉無重力のように慣性のようにそのまま池面を離れてゆく舟として。最後に好きな歌を一首。
漆黒のぶどうひとつぶ口に入れ敗れつづける決心をする 江戸雪